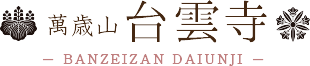令和七年三月二十日は春季彼岸法要を厳修致しました。彼岸入りからお寺参りやお墓まいりをされる方が増え、彼岸法要当日もたくさんの方がお参りに来られました。
彼岸とは”悟りの世界”という意味がございます。そしてこの世に行きながら、その悟りの世界に近づく、仏様の境涯に至る、そのための六つの修行のことを『六波羅蜜』といいます。布施という他人に施すという事には、物や心だけでなく、まなざしや柔らかい表情や優しい言葉などもそうです。






法話をして下さった願成寺 住職 佐藤 直哉老師 のお話の一部を紹介させて頂きます。


日本における長寿祝い
日本には以下のような長寿祝いがあります。六十一歳(満六十)の還暦(かんれき) 七十歳の古稀(こき) 七十七歳の喜寿(きじゅ) 八十歳の傘寿(さんじゅ) 八十八歳の米寿(べいじゅ)
九十歳の卒寿(そつじゅ) 九十九歳の白寿(はくじゅ) 百歳の百寿(ももじゅ)または紀寿(きじゅ) などです。そのいわれは、次の通りです。
還暦は六十年で十干十二支(じっかんじゅうにし)が一巡して元の暦に還ることに由来、古稀は杜甫(とほ)の詩である「人生七十古来稀也」(じんせいななじゅうこらいまれなり)より、
喜寿は喜の草書体が七十七と読めることから、傘寿は傘の略字を分解すると八十となるから、米寿は米の字を分解すると八十八となるから、
卒寿は卒の略字の卆が九十と読めるから、白寿は百という字から一をとる、引くと白になることから、紀寿(百寿)は紀が一世紀を意味することに由来する。
人生百年時代と言われる現代を生きる私たち。
明るく前向きにこれからの長寿時代を過ごしてまいりましょう。合掌